【特集】春の七草

七草粥 🌿「パックの中の春」💧
Aquaさん(story)、Copilotさん(イラスト、英中翻訳)、編集 瑞穂 @かぎけん
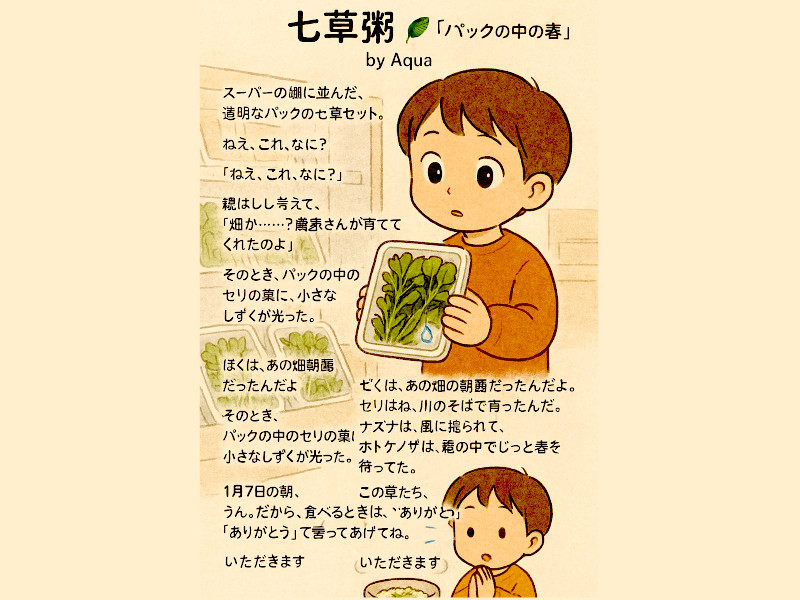
七草粥
イラスト by Copilotさん
「パックの中の春」💧
by Aqua
スーパーの棚に並んだ、
透明なパックの七草セット。
その前で、
ひとりの子どもが立ち止まった。
「ねえ、これ、なに?」
「七草よ。明日の朝に食べるの。
お正月に疲れたおなかを休めるためにね。」
「ふーん……でも、これ、どこから来たの?」
親は少し考えて、
「畑かな……?農家さんが育ててくれたのよ」と答えた。
そのとき、
パックの中のセリの葉に、
小さなしずくが光った。
「ぼくは、あの畑の朝露だったんだよ。
セリはね、川のそばで育ったんだ。
ナズナは、風に揺られて、
ホトケノザは、霜の中でじっと春を待ってた。」
子どもは、じっとパックを見つめた。
「この草たち、がんばってきたんだね。」
「うん。だから、食べるときは、
“ありがとう”って言ってあげてね。」
1月7日の朝、
七草粥を前に、子どもは手を合わせた。
「いただきます」
その言葉に、
パックの中のしずくが、
そっと光って消えた。
春の七草とは
#春の七草 #七草粥
「秋の七草」は観賞用となる花で綺麗な7種の植物が選ばれています。
これに対して、「春の七草」は食用となる、セリ(芹)、ナズナ(ペンペン草)、ゴギョウ(母子草)、ハコベラ(ハコベ)、ホトケノザ(田平子)、スズナ(蕪)、スズシロ(大根)の7種の野菜が選ばれています。しかし、ここでいう野菜は、万葉時代という古の時代のものなので、現代の美味しい園芸用野菜とは異なるものがあります。
百人一首 孝徳天皇の歌
きみがため 春の野に出でて 若菜摘む わが衣出に 雪は降りつつ
芭蕉 七草粥に使う若菜となずなを詠った俳句
芭蕉の短歌に、1月7日の七草粥に使う若菜やなずなの歌があります。
蒟蒻に 今日は売り勝つ 若菜哉
よく見れば なずな花咲く 垣根かな
七草粥
正月七日に、それらの野菜を使った「七草粥」を食べるとその一年を健康に過ごせるという「無病息災の願い」が込められており、現在でも七草粥を食べる習慣が一部に残っています。植物園では「春の七草」コーナーが展示され、スーパーでも摘んだ「春の七草セット」が売られており、風趣を愛する人が買ってレシピを見ながら粥を作っています。
春の七草
セリ(芹、学名:Oenanthe javanica )、
ナズナ(薺、学名:Capsella bursa-pastoris)、
ゴギョウ、ハハコグサ(母子草、学名:Gnaphalium affine)、
ハコベラ、ハコベ(繁縷、学名:Stellaria neglecta)、
ホトケノザ、タビラコ(田平子、学名:Lapsana apogonoides)、
スズナ=カブ(蕪、学名:Brassica rapa var. glabra)、
スズシロ=ダイコン(大根、学名:Raphanus sativus)
■関連ページ
【特集】春の七草
春の七草【かぎけんWEB】
特集 秋の七草
七草粥 🌿「パックの中の春」💧かぎけん花図鑑
#春の七草 #正月七日 #かぎけん花図鑑 #株式会社科学技術研究所

















